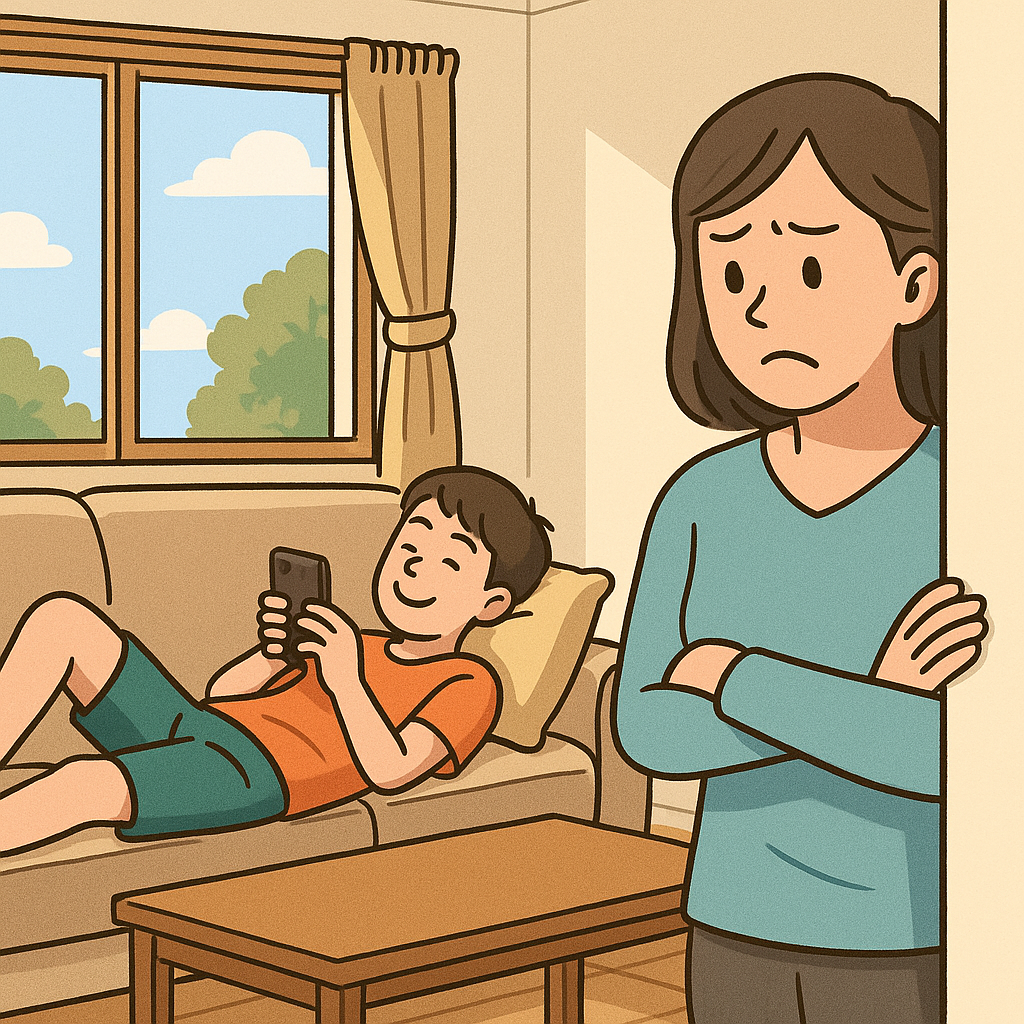こんにちは。不登校支援をしている私たちのもとには、「子どもは家で楽しそうにしてるけど、このままで大丈夫なんでしょうか?」というご相談がよく届きます。
今回は、そんな「保護者だけが困っているように見える不登校」のケースをテーマに、支援現場から見えてきたことをお伝えします。
子どもは本当に「困ってない」のか?
不登校が始まった直後、本人は苦しみを抜けた直後の“落ち着き状態”にいます。
それまで、学校に行きながら無理をしていた時期は、実はものすごくストレスを抱えていたんですね。
そのストレスが一気に軽減されたので、「あー、ようやく終わった。落ち着ける」という感覚です。
だからこそ、YouTubeを見たり、ゲームをしたり、笑顔で話しかけてくる。
一方で保護者はその頃からストレスが増し始めます。
「勉強は?」「進路は?」「私は仕事を辞めるべき?」——いろんな不安が押し寄せてきます。
そんな中で、楽しそうにしているわが子を見て、「なんであなたはそんなにノホホンとしてるの⁉」とイライラしてしまう。それは当然のことだと思います。
長期化の背景にある“次の一歩”の重たさ
では、家で落ち着いて半年、1年…と経っても子どもが動き出さないのはなぜか?
それは「次の一歩がわからない、怖い、だから動けない」という状態だからです。
本人にとっては、不登校になった自分を変える方法や、新しい環境をつくる方法なんて、想像もつかないことなんです。
小中学生や高校生が、自分で人生を再設計するのは無理があります。
なので、「なんで動かないの?」ではなく、「どうやったら動けるようになるか」を一緒に考える視点が必要です。
本人のしんどさを“数値”で見える化する

私たちの支援では、本人と信頼関係ができてから、「何がどれくらいしんどかったのか」を具体的に聞いていきます。
たとえば:
- 担任の先生との関係:〇〇%
- クラスの同級生との関係:〇〇%
- 家族との関係:〇〇%
- 自分の内面のしんどさ:〇〇%
こうやって“数値化”することで、本人自身も「あ、自分ってここがつらかったんだな」と客観視できるようになります。
以前あった例では、「担任以外の先生が7割しんどい」「自分の内面の不安が3割」という答えがありました。
これは後に、他人の目を気にしすぎる“他者中心性”という特性が強く出ていたとわかりました。
本人が“動き出す”スイッチを入れるには
不登校の本人も、「一生このままでいたい」と思っているわけではありません。
多くの子が「学校が楽しくてラクなら行くよ」と話してくれます。
つまり、「つらい場所に戻る意味がない」と判断しているだけなんですね。
では、どうすれば本人が「次の一歩」を踏み出せるか?
ポイントは、本人の人生がもっと面白くなるために必要なことを一緒に見つけていくことです。
ハッカー少年の“次のステージ”
以前、20歳のある男の子がいました。
学校には行っていませんが、趣味でゲーム改造やプログラミングを通じてハッキング技術を身につけていました。
最初は「この生活がずっと続けばいい」と言っていた彼ですが、話を重ねていくうちに、
「もっと人生を面白くするには?」と自分で考えるようになっていきました。
その後、ホワイトハッカーとして活動を始め、依頼を受けるサイトを立ち上げ、ネット上では有名な存在に。
仕事が来るようになったら、今度は「企業と契約する打ち合わせ」が必要になり、そこでまた一歩踏み出すことになりました。
「本人の得意なこと」が扉を開いた好例です。
まとめ:本人のタイミングを信じて、伴走する
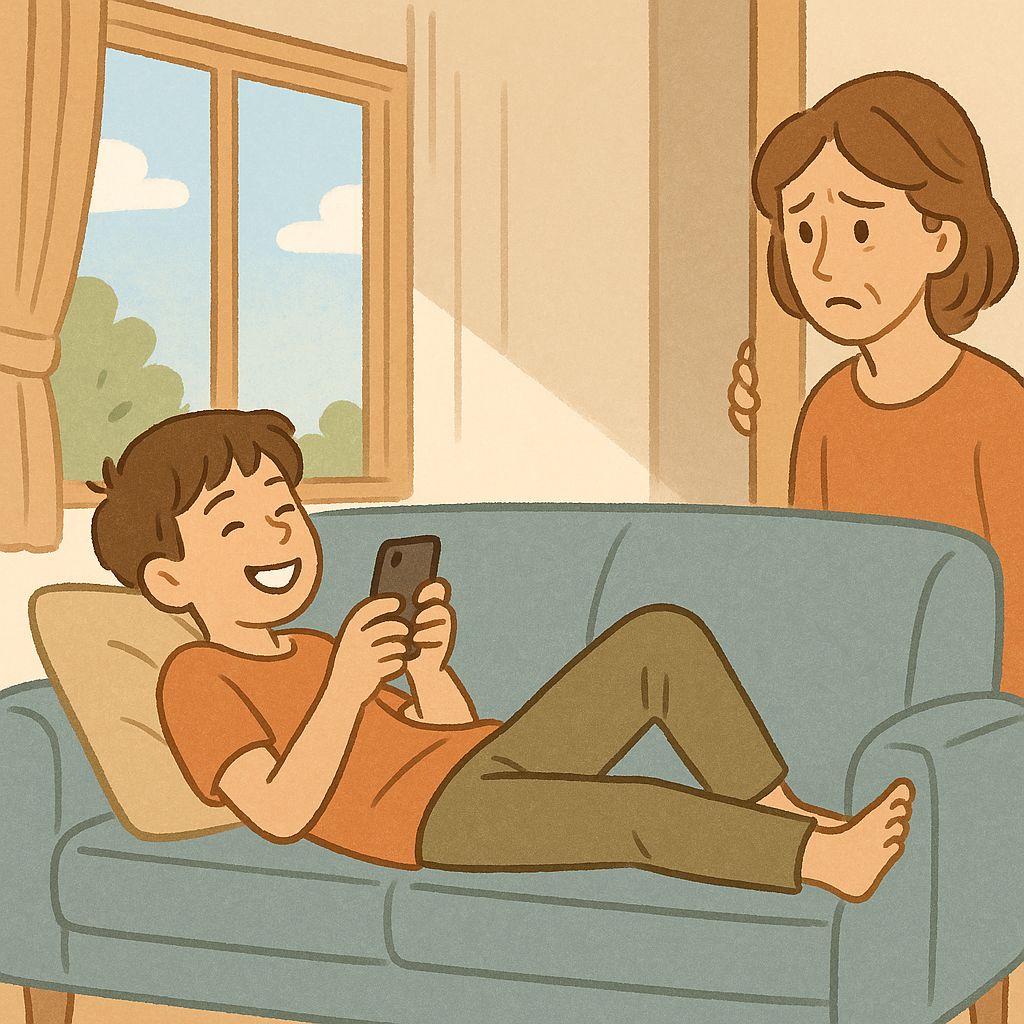
不登校の時期、「困ってないように見える」わが子を見て、もどかしく感じる気持ちは本当によくわかります。
でも、その状態は「ただのサボリ」ではなく、ストレスの谷からようやく抜けた“休息の時期”。
ここからどう立ち上がるかは、本人の中にある“おもしろく生きたい”という気持ちをどう引き出せるかにかかっています。
一人で悩まず、ぜひ私たちにご相談ください。
子どもたちの“動き出す瞬間”を、たくさん見てきました。きっと道は開けます。